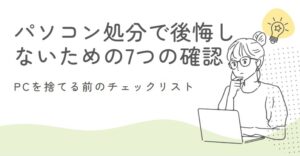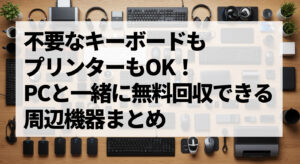【2025年10月】Windows 10サポート終了で不要PCが大量発生?無料でパソコン回収する方法とは
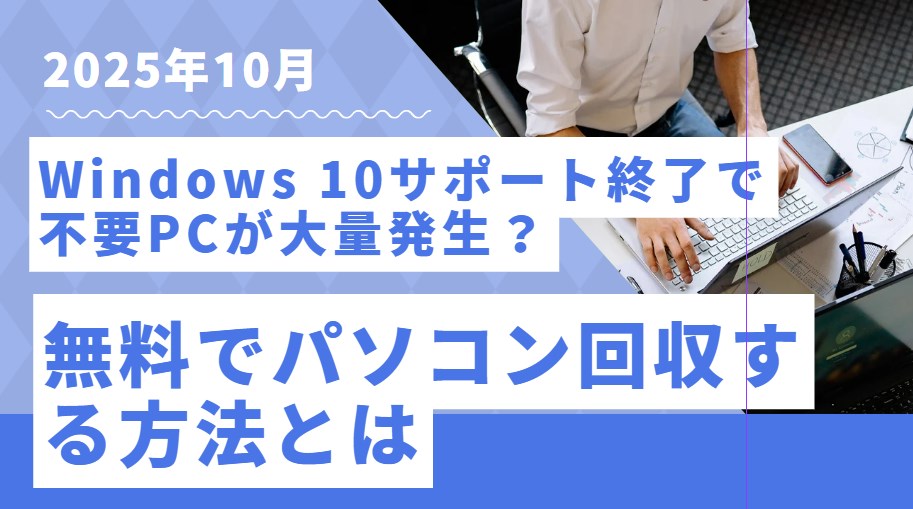
「2025年10月14日」——この日を境に、長年多くのユーザーに親しまれてきたWindows 10のサポートが正式に終了します。
この発表により、全国の企業や団体、さらには個人の間でも“不要になるPCの扱い”について頭を悩ませる声が急増しています。
とくに、Windows 11への移行にあたっては、対応するハードウェア要件が厳しく、比較的新しいPCであってもアップグレードができないケースが多数。結果として、大量のパソコンが不要となり、処分や管理の課題が浮き彫りになっています。
当、北海道PC回収センターでは北海道内の事業所・会社様・個人のPCを「無料で回収」しています。
「処分にお金がかかる」「社内で放置している」…そんなお悩みを抱えている方にとって、安心と解決の糸口になれば幸いです。
Windows 10のサポートは2025年10月14日で終了
Windows 10のサポート終了日は、2025年10月14日と公式に発表されています。これは、Microsoftが提供していた機能更新やセキュリティパッチなど、あらゆるサポートが打ち切られることを意味します。
ここで注意すべきは、「サポートが終わっても使えなくなるわけではない」という誤解です。たしかにPC自体は引き続き動作しますが、重大なセキュリティリスクにさらされる状態になります。
たとえば、新たなウイルスやマルウェアへの対処が行われなくなり、外部からの不正アクセスや情報漏洩といった被害に直結する危険性が高まります。
特に法人や団体にとっては、機密情報の漏洩や業務システムの停止といった事態に発展する恐れがあり、「使えなくなる前に手を打つ」ことが重要です。
そのため、Microsoftもサポート終了を前提に、後継のWindows 11への移行を強く推奨しています。
今後、Windows 10を搭載したまま放置されたPCは「使えない上に危険な機器」と化していくことになりかねません。サポート終了の意味を正しく理解し、今のうちから準備を進めることが必要です。
Windows 11への移行とその壁
Windows 10の後継として登場したWindows 11は、より強化されたセキュリティ機能や洗練されたUI(ユーザーインターフェース)を特徴としています。Microsoftは公式に、Windows 10からの移行を推奨していますが、実際にはその「移行」が大きなハードルになっています。
最大の理由は、Windows 11のシステム要件の厳しさです。特に問題となるのが「TPM 2.0(セキュリティチップ)」や「対応するCPU」の制限。これにより、2015年~2018年頃に購入した比較的新しいWindows 10マシンでさえ、アップグレード対象外となっているケースが多発しています。
結果として、多くの企業や団体、個人がやむなくPCの買い替えを決断することになります。特に法人にとっては、一度に数十台、数百台規模の買い替えが発生することもあり、業務やコストへの影響も少なくありません。
こうして買い替えが進む中で、「では古いPCはどうするのか?」という問題が浮上します。
再利用も難しく、社内に放置されるケースが後を絶ちません。しかし、こうしたPCを適切に処分しないことには、情報漏洩のリスクやスペースの無駄といった新たな問題も生まれます。
Windows 11への移行は避けられない流れである一方で、それに伴う“不要PCの山”という新たな課題にどう向き合うか——これが今、多くの現場で問われています。
不要PCをそのまま放置すると起きる問題
Windows 10搭載の古いパソコンを買い替えた後、「とりあえず保管しておこう」と社内や自宅の片隅に置いたままにしていませんか?
実は、この“何となく放置”が、思わぬリスクを招く可能性があります。
セキュリティリスクの温床に
サポートが終了したWindows 10搭載PCは、セキュリティ更新が一切行われない状態です。インターネットに接続されていなくても、USB機器経由でのウイルス感染や情報漏洩の可能性が残ります。企業や団体の場合、古い端末から顧客情報や業務データが漏れた場合、法的責任や信用失墜にもつながりかねません。
情報漏洩の危険性
仮にPCを廃棄する場合でも、ハードディスクにデータが残ったままでは非常に危険です。初期化しても完全には消去されないケースもあり、専門的な知識を持つ第三者に復元される可能性があります。とくに法人の場合、従業員情報、契約書類、取引履歴など、極めてセンシティブなデータが含まれていることも。
不要なコストやスペースの浪費
「そのうち何とかしよう」と保管を続けることで、オフィスや倉庫のスペースを圧迫するだけでなく、やがては処分費用がかかる可能性もあります。
特に法人では廃棄証明書が必要なケースもあり、専門業者に依頼すると1台あたり数千円のコストが発生することも少なくありません。
無料でPCを大量回収してくれる「北海道PC回収センター」とは
不要になったWindows 10搭載PCの処分に悩む企業や団体にとって、心強い味方となるのが「北海道PC回収センター」です。
このサービスは、法人・個人を問わず、無料でパソコンの大量回収に対応している点が大きな特徴です。
■ サービス概要
北海道PC回収センターでは、Windows 10のサポート終了に伴って発生する大量の不要PCを対象に、回収・運搬・ハードディスクの破壊までを一括対応しています。
「処分費用がかからない」「スピーディに対応してくれる」といった点で、多くの企業や団体から評価を得ています。
■ なぜ無料なのか? 他社との違い
「無料というのは逆に不安…」という声もあるかもしれませんが、その仕組みは明確です。
北海道PC回収センターでは、回収したPCを再資源化・リユース可能な部品として再利用することでコストを回収しています。
そのため、利用者側に費用を求めることなく、高品質なサービスを実現できているのです。
また、他社と比較した際の明確な強みとしては以下の点が挙げられます。
- データ消去にも完全対応(物理破壊機器を使用・破壊証明書は有料)
- 北海道内全域に対応
- 小規模〜大規模まで柔軟に対応可能
- 迅速な回収スケジュール
■ 対象エリアと回収の流れ
北海道PC回収センターは、その名の通り北海道内全域に対応しており、札幌市内だけでなく地方の事業所からの依頼も多数実績があります。
回収の流れも非常にシンプルです。
- ホームページまたは電話でお問い合わせ予約
- 回収対象機器の確認と日程調整
- スタッフが現地に伺い回収・運搬
- 破壊証明書の発行(必要に応じて)
北海道PC回収センターの利用手順
不要PCの処分を考えたとき、「手続きが面倒なのでは?」と二の足を踏んでしまう方も少なくありません。
しかし、北海道PC回収センターでは、誰でも簡単に、そしてスムーズに利用できるフローが整っています。
以下に、回収サービスを実際に利用する際の流れをご紹介します。
ステップ1:お問い合わせ
まずは、北海道PC回収センターの公式サイト、または電話・メールでお問い合わせください。
この段階では、以下のような情報を用意しておくとスムーズです。
- 回収したいPCの台数・種類
- 所在地(回収先住所)
- 希望の回収日程
ステップ2:回収内容の確認と日程調整
担当スタッフがヒアリングを行い、機種の対応可否や数量などの詳細確認を行います。
その後、ご希望に合わせて訪問日程を調整し、回収の準備に入ります。
ステップ3:出張回収/郵送回収/持ち込み回収
指定日にスタッフが現地へ訪問する出張回収、PCを梱包し郵送してもらう着払い回収・事業所窓口に直接持ち込んでもらう持ち込み回収の3タイプがあります。
大量回収にも対応しており、10台以上でも一括で対応可能です。
このとき、物理的な破壊や安全な運搬処理を行うため、社内での作業も最小限で済みます。
ステップ4:データ消去と証明書の発行(必要に応じて)
回収後、破壊装置(クラッシュボックス)によるハードディスクのデータ消去作業を実施。
ご希望があれば、データ消去の証明書や回収証明書も発行してもらえるため、情報管理や監査対応にも万全です。
このように、PCの種類や台数を問わず、シンプルかつ安心して依頼できるプロセスが整っています。
煩雑な手続きを避けたい方、社内での工数をかけたくない方にとって、非常に有用なサービスといえるでしょう。
まとめ
Windows 10のサポートが2025年10月14日に終了することで、全国で大量の不要PCが発生することは避けられません。
特に、Windows 11へのアップグレードが難しい環境にある方々にとって、古いPCの扱いは避けては通れない課題です。
サポートが終了したPCをそのまま放置してしまうと、セキュリティリスクや情報漏洩、スペースの無駄、処分コストの発生など、数多くの問題が生じます。
だからこそ、今のうちから安全かつ無料で対応してくれるサービスを知っておくことが重要です。
もしあなたのもとに、使われずに放置されたWindows 10搭載PCがあるなら、今すぐ「北海道PC回収センター」にご相談ください。
- 大量回収にも無料対応
- データ消去や証明書発行も可能
- 北海道内全域対応、スピード回収
煩わしい手続きやコストは一切不要です。
「まずは話を聞いてみたい」だけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 札幌市を拠点として、北海道内のご家庭や会社様を対象に、不要になったパソコンの無料回収・再資源化リサイクルを行っています。「もう使わない古いパソコンがある」、「情報漏洩が心配」、「自治体の捨て方が分かりづらい」ご連絡ください。
最新の投稿
 札幌引越2026年1月16日【2026年春・引越し予約受付中】札幌からの単身引越し・不用品回収は「フェリス」へ!
札幌引越2026年1月16日【2026年春・引越し予約受付中】札幌からの単身引越し・不用品回収は「フェリス」へ!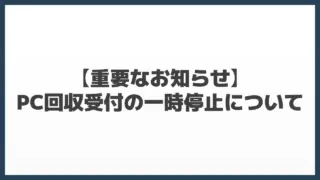 お知らせ2025年12月12日【重要なお知らせ】PC回収受付の一時停止について
お知らせ2025年12月12日【重要なお知らせ】PC回収受付の一時停止について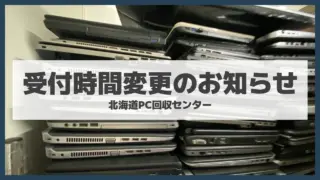 お知らせ2025年11月16日北海道PC回収センター 受付時間変更のお知らせ
お知らせ2025年11月16日北海道PC回収センター 受付時間変更のお知らせ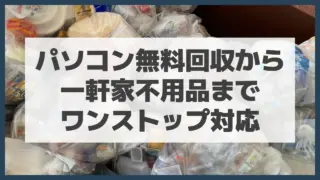 不用品回収丸ごと2025年9月24日北海道PC回収センターはパソコン無料回収だけじゃない!パソコン無料回収から一軒家不用品までワンストップ対応
不用品回収丸ごと2025年9月24日北海道PC回収センターはパソコン無料回収だけじゃない!パソコン無料回収から一軒家不用品までワンストップ対応